教養専門科目群
グローバル?コネクティビティ領域
Global Connectivity Program: GC
人、文化とコミュニケーションと最先端技術に関連する科目群を通して、両者における接続性(コネクティビティ)を学ぶ
人類は有史以来、言語やコミュニケーション手段を発達させながら多様な文化を育んできました。一方で近年はデジタルテクノロジーやAI、ビックデータ等、各種技術の飛躍的な発展が私たちの生活や社会に大きな変化をもたらしています。
本領域では、文化や文学、哲学といった生きることの意味や価値を追求する人文科学と、私たちの現代社会に急速に浸透しつつあるAIや最先端技術を同じ土俵で学修します。分野の違うこれらの科目を接続させながら学ぶことにより、ますます発展するであろう各種技術が私たちの日常生活、政治、経済に及ぼす影響を多角的な視点で分析し、それらをどのように活用してこれからの社会を創造していくのかを洞察する力を身につけます。
教員からのメッセージ
「文系」「理系」の壁を越えて
今、未来への備えとしてどのような教育が求められているのでしょうか。未来を予測するのは難しいことですが、技術の進歩が加速する中、テクノロジーがこれからの社会に及ぼす影響はますます大きくなるでしょう。学生たちが卒業後の人生において成功を収めるには、現在の「文系」「理系」の壁を越えて学ぶ必要があります。
GC領域のカリキュラムでは、最新のデジタルテクノロジーを駆使すると同時に、文化などの人文科学を深く理解し、広範囲にわたる様々な分野を接続させながら学ぶことにより、変化する社会に柔軟に適応?対応できるような学生を育てていきます。人文科学は、テクノロジーと共存する私たちの生活を有意義なものにし、テクノロジーを改めて理解することは、学生たちにとって未来への鍵となるでしょう。
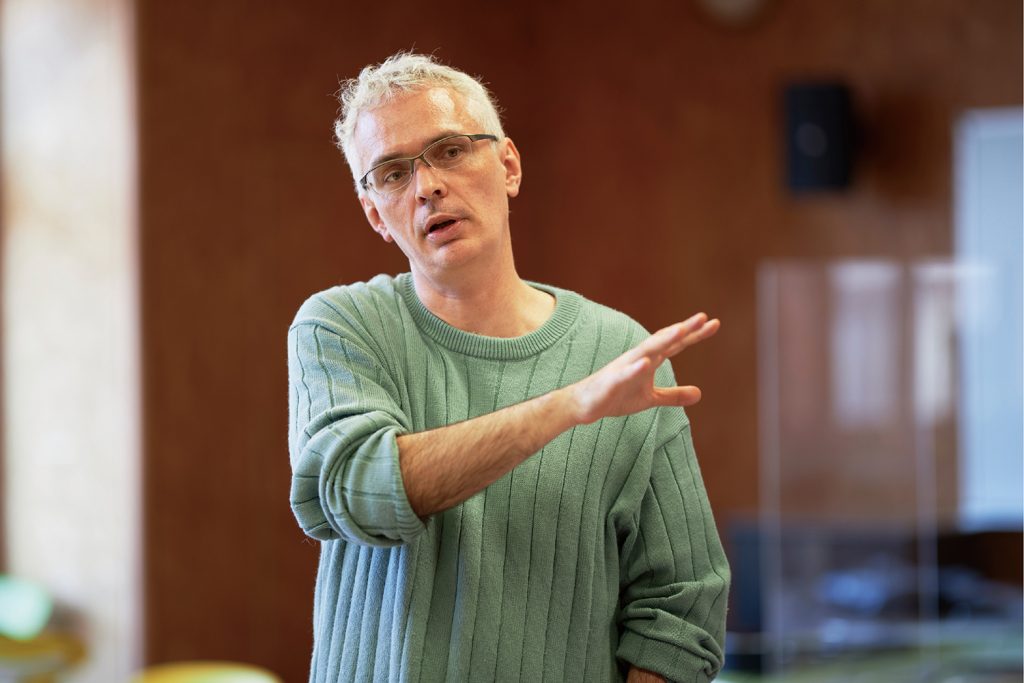
現代社会において、「つながり(Connectivity)」のデジタル化と常態化、そしてオートメーション、人工知能(AI)の台頭に代表されるようなデジタルテクノロジーの急速な進歩は、私たちに難しい問いを突きつけます。「新しい技術と関係性から恩恵を受けるのは誰か?」「誰が取り残されるのか?」「どのようにして人間の価値観に基づいた社会を形成することができるのか?」「人間の判断をどの範囲までAIに置き換えるべきか?」本領域ではこのような答えのない疑問に対して、人文科学とテクノロジーのつながりの探求というアプローチから、考察を深めていきます。
批判的思考、論理的分析、文化理解だけでなく、効果的なコミュニケーションによるクリエイティブな課題解決力は、生涯に渡る学びの土台を作るでしょう。本領域で学生は、個々の人生、地域社会、そして世界において、有意義かつ持続可能な影響を与えるために必要な知識とスキルを修得します。
※ここでは、英文メッセージの日本語訳を掲載しています。
フローラン?ドメナック Dr. Florent DOMENACH
グローバル?コネクティビティ領域長?ICTコーディネーター/教授
学生インタビュー
井澤 円花(京都府/2020年入学)
本学への志望動機は?
日本にいながら英語でリベラルアーツ教育を受けられる点に惹かれ、AIUへの進学を決めました。私は高校での進路選択の際、将来自分が何をしたいかはっきりと分からない中、大学での学びを一つの分野に絞ることに抵抗がありました。そのため、文理問わず、幅広い分野を学べるAIUのカリキュラムは非常に魅力的でした。また、英語で学び、考え、意見を発信する力が養えるAIUは将来、英語をツールとしてグローバルに活躍したい私にとって、必要な力が身につけられる場所だと思いました。

特に印象に残ったGC領域の授業は?
「JAS200 日本の文学 Ⅰ」です。日本の文学作品を英語で読み、その奥深さについて英語でクラスメイトとディスカッションできるところが魅力です。二葉亭四迷の『浮雲』や志賀直哉の『城の崎にて』といった名作を英語で読むことで、原文と英訳の表現の違いなど、日本語で読む時とは違う面白さがありました。文学作品に対する考えを日本語では言語化できても、英語では上手く伝えられない時は、留学生の回答から、自分の考えを的確に伝えるための英語表現を学んでいました。
AIUを目指す皆さんに伝えたいこと
AIUの魅力は自分の「学びたい」が叶う環境が整っていること、また、AIU独自のコミュニティにあると感じます。幅広い分野のテーマを取り扱う授業が開講されているため、大学に入学して、新たに学びたいと思った分野の授業に出会えると思います。加えて、AIUには自分では考えつかないような活動をしている学生が多くいて、そんな仲間の姿勢から日々刺激を受けています。学生同士が互いの挑戦を応援し合えるとてもあたたかいコミュニティです。


